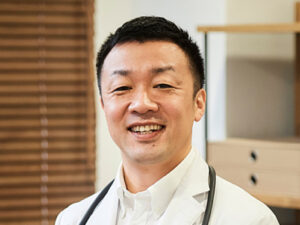「寒くなると、 どうしても動くのが億劫…」
気温が下がってくる時期になると、
こんな言葉を患者さんから聞く機会が増えます。
せっかく運動習慣がついてきたのに、
寒さをきっかけに離脱してしまう。
医療スタッフは「寒さの壁」に
どう向き合えばよいのでしょうか。
寒い時期の運動離れの実態
理学療法士の佐藤さん(仮名)は、
毎年この時期になると、
ある傾向に気づいていました。
リハビリの予約キャンセルが増えるのです。
特に高齢の患者さんからの
「今日は寒いので…」という連絡。
「夏から秋にかけて順調だった方が、
急に来なくなることがあるんです」
実際、気温が下がると、
運動量が減少することは
多くの研究で示されています。
寒さが運動を妨げる理由は、
いくつか考えられます。
身体的な要因
寒さで筋肉が硬くなり、
動き始めるまでのハードルが高くなります。
そして、心理的な要因
「寒いから外に出たくない」
心理的抵抗感が生まれます。
体調管理の不安もあります
「寒い中で運動したら風邪を引くのでは」
と、不安を感じる方もいます。
生活リズムの変化
日が短くなることで、
運動に充てる時間が
確保しにくくなります。
看護師の田中さん(仮名)が担当する
糖尿病患者の木村さん(仮名・62歳男性)も、 その一人でした。
9月までは毎朝のウォーキングを続けていた木村さん。
しかし10月後半から、
徐々に歩く回数が減少。
「朝が寒くて、布団から出るのがつらくて。 一度休むと、そのまま…」
HbA1cの数値も、
少しずつ上昇傾向を
示していました。
室内でできる運動の提案方法
田中さんは、 木村さんに一つの提案をしました。
「無理に外を歩かなくても大丈夫です。
室内でできる運動もありますよ」
最初、木村さんは戸惑いました。
「室内で運動?何をすればいいんでしょうか。
ジムに通うのは、ちょっと…」
田中さんは、
自宅でできる簡単な運動を
いくつか紹介しました。
その場での足踏み。
テレビを見ながら、
その場で足踏みするだけ。
それだけでも効果があります。
階段の昇り降りも運動です。
自宅に階段があれば、
それだけで昇降運動です。
椅子を使った運動もあります。
椅子に座ったり立ったりを繰り返す
スクワットのような動作です。
ストレッチも効果的です。
身体を温めながら、
柔軟性も高められます。
「これなら、朝起きてすぐにできますね。
外に出る準備もいらないし」
木村さんの表情が、
少し明るくなりました。
室内運動を提案する際のポイントがあります。
ハードルを下げる。
「5分でいい」
「テレビを見ながらでいい」
などと、気軽にできることを強調します。
具体的な方法を示す。
「その場足踏み」など、
イメージしやすい運動を提案します。
生活の中に組み込むと続けやすい。
「朝のニュースを見ながら」など、
既存の習慣に紐づけるのです。
しっかり効果を説明する。
「外でのウォーキングと同じ効果が期待できる」と
伝えることで、納得感が生まれます。
管理栄養士の山本さん(仮名)は、
室内運動と食事指導を組み合わせています。
「寒い時期は、身体が温まる食材と
室内での運動を組み合わせることで、
代謝を維持しやすくなります」
多職種で連携しながら、
包括的なアプローチを
提供することが効果的です。
寒暖差による体調管理のポイント
木村さんが室内運動を始めて2週間が経った頃。
田中さんは、 もう一つ重要なアドバイスをしました。
「寒暖差にも注意が必要です。
特に朝は、急な温度変化に気をつけてください」
寒い時期の運動には、
体調管理上の注意点があります。
急激な温度変化を避ける。
暖かい室内から急に寒い屋外に出ると、
血圧が急上昇する可能性があります。
ウォームアップを丁寧に
寒さで筋肉が硬くなっているため、
いつも以上に準備運動が重要です。
水分補給を忘れない
寒いと喉の渇きを感じにくいですが、
運動中の水分補給は必要です。
体調に合わせて調整
寒さで体調を崩しやすい時期なので、
無理をしないことが大切です。
理学療法士の佐藤さんは、
高齢患者さんに特に注意を促しています。
「寒い日の朝一番の運動は避けて、
部屋が温まってからにしましょう。
また、運動前の軽いストレッチで、
身体を温めることをお勧めします」
実際、心筋梗塞や脳卒中は、
寒暖差の大きい時期に増加する傾向があります。
運動は健康に良いものですが、
やり方を間違えると危険もあります。
医療スタッフとして、
安全な運動方法を
伝えるのも重要な役割です。
気分の落ち込みと運動の関係
11月も半ばを過ぎた頃。
田中さんは、別の患者さんから
こんな相談を受けました。
「なんだか、最近気分が沈みがちで
運動する気力が湧かないんです」
相談者は、橋本さん(仮名・55歳女性)。
血圧管理のため、
運動を勧められている方でした。
日が短くなり、
日照時間が減る時期。
実は、気分の落ち込みと運動意欲の低下には、
関連があると考えられています。
日光を浴びる時間が減ると、セロトニンという
神経伝達物質の分泌が減少します。
これが、気分の落ち込みや
意欲の低下につながる可能性があるのです。
田中さんは、 橋本さんにこう伝えました。
「実は、運動で気分の改善が期待できるんです」
運動が気分に与える効果は、
いくつかの研究で示されています。
神経伝達物質の分泌促進。
運動により、セロトニンやドーパミンなどの
分泌が促進されると考えられています。
ストレス軽減
適度な運動は、
ストレスホルモンの分泌を
調整する効果があります。
達成感の獲得
「今日も運動できた」
という小さな達成感が、
自己肯定感を高めます。
生活リズムの維持
規則正しい運動習慣は、
生活全体のリズムを整えます。
「気分が沈んでいる時こそ、
軽い運動が助けになることがあります。
無理のない範囲で、5分でも
身体を動かしてみませんか」
橋本さんは、半信半疑ながらも、
朝の簡単なストレッチから
始めることにしました。
多職種連携による包括的サポート
寒い時期の運動継続支援では、
多職種での連携が特に重要です。
医師は、運動の安全性について
医学的な観点から助言します。
看護師は、日々の体調管理と
運動習慣の継続をサポート。
理学療法士は、安全で効果的な
運動方法を具体的に指導します。
管理栄養士は、身体を温める食事と
運動の組み合わせを提案します。
薬剤師は、薬の影響や
運動時の注意点を説明します。
佐藤さんのクリニックでは、 月に一度、
多職種カンファレンスを開いています。
「運動習慣が途切れがちな患者さんについて、
それぞれの視点から情報を共有するんです。
例えば『最近来なくなった』という情報があれば、
看護師から連絡を入れてもらったり」
このような連携は、 患者さんが孤立することなく、
継続的なサポートを受けられる体制が生まれます。
薬だけでない選択肢として
木村さんは、 室内運動を始め3ヶ月経過。
HbA1cの数値は改善し、
主治医からも良い評価を受けています。
「薬の量を増やす話も出ていたんですが、
運動を続けたおかげで、今の量で管理できています」
もちろん、薬が必要な場合には
適切に使用することが大切です。
しかし、生活習慣の改善によって、
薬に頼る度合いを減らせることも。
患者さん一人ひとりの状況に合わせて、
薬と運動、食事など、複数の選択肢を組み合わせる。
それが、現代の医療に求められる
アプローチではないでしょうか。
田中さんは今日も、
「寒くて動けない」と話す患者さんに、
丁寧に寄り添っています。
「大丈夫ですよ。 外に出なくても、できることはあります。
一緒に、あなたに合った方法を 探していきましょう」
まとめ
寒い時期の運動離れは、
多くの患者さんが経験する課題です。
医療スタッフとして、「寒いから仕方ない」で終わらせず、
室内でできる運動を提案したり、安全な運動方法を伝えたり、
気分との関連も考慮したサポートが大切です。
多職種で連携しながら、
患者さんの状況に合わせた対応。
そして、薬だけでなく、
運動という選択肢を提示し続けること。
寒い時期だからこそ、 医療スタッフの声かけが、
患者さんの健康習慣を 支える大きな力になるのです。