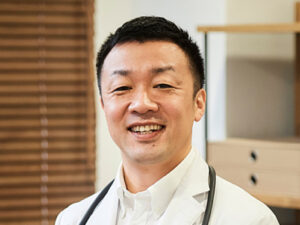「昨日、 家で転びそうになって…」
外来でこんな話を聞いたことは、 ありませんか。
高齢の患者さんからの、何気ない一言。
しかし、この「転びそうになった」は、
重大な事故の前兆かもしれません。
医療スタッフとして、
転倒予防にどう関われば
良いのでしょうか。
転倒リスクと運動の関係
看護師の山田さん(仮名)は、
ある患者さんが気になっていました。
75歳の鈴木さん(仮名・女性)。
定期的に通院している方ですが、
最近、歩き方に変化が見られたのです。
「以前より歩幅が狭くなって、
足を上げる高さも低い気がする」
山田さんの観察は、的確でした。
転倒リスクが高まるサインは、
いくつかあります。
歩行の変化
歩幅が狭くなる、足が上がらなくなる、
歩くスピードが遅くなるなどの変化です。
バランス能力の低下
片足立ちができない、
ふらつきが増える などの症状です。
筋力の低下
椅子から立ち上がるのに時間がかかる、
階段の上り下りがつらくなるなどの変化。
体力の低下
疲れやすくなる、活動量が減る
などの全身的な変化です。
実際には、これらの変化の多くは、
運動で改善できると考えられています。
筋力トレーニング
下肢の筋力を維持・向上させることによって、
転倒リスクが低減すると考えられるからです。
バランストレーニング
片足立ちやタンデム歩行など、
バランス能力を高める運動が効果的です。
柔軟性の向上
ストレッチによる、
可動域維持も重要です。
歩行訓練
正しい歩き方を意識することで、
安定した歩行が可能になります。
筋力・バランス能力の維持方法
山田さんは、 鈴木さんに声をかけました。
「最近、足腰の調子はいかがですか?」
鈴木さんは、 少し不安そうに答えました。
「実は、ちょっとした段差でつまずくことが 増えて…。
年だから仕方ないと思っていたんですが」
「仕方ない」で済ませるのではなく、
適切な運動で改善できる可能性があります。
山田さんは、 理学療法士の田口さん(仮名)に相談しました。
田口さんは、鈴木さんの身体機能を評価し、
自宅でできる運動プログラムを提案しました。
椅子を使ったスクワット
椅子に座った状態から立ち上がり、
ゆっくり座る動作を繰り返します。
これで、下肢の筋力を維持・向上させます。
片足立ち練習
壁や手すりに手を添えて、
片足で立つ練習をします。
最初は数秒から始め、
徐々に時間を延ばしていきます。
かかと上げ運動
立った状態で、かかとを上げ下げする運動です。
ふくらはぎの筋力強化と、
バランス能力の向上が期待できます。
次は、足指の運動です
タオルを床に置き、
足の指でたぐり寄せます。
足裏の筋力を高め、
踏ん張る力を向上させます。
「どれも、テレビを見ながらでもできる運動ですよ。
毎日5分でいいので、続けてみてください」
田口さんの説明を聞いて、
少し安心した様子でした。
「これなら、私にもできそうです」
重要なのは、高齢者に合わせた難易度設定です。
最初から高いハードルを設定せず、
「これならできる」と思える内容。
これが、継続の大きな鍵となります。
多職種で取り組む転倒予防
鈴木さんの転倒予防には、
多職種でのアプローチが行われました。
医師は、転倒リスクを高める
薬の影響がないか確認しました。
看護師の山田さんは、
日常生活での注意点を
アドバイスしました。
理学療法士の田口さんは、
具体的な運動方法を指導。
薬剤師は、 めまいや眠気を
起こしやすい薬の説明を。
管理栄養士は、筋肉を維持するための
たんぱく質摂取について助言しました。
それぞれの専門性を活かした
チームアプローチが効果的です。
また、定期的な評価も重要です。
山田さんは、鈴木さんの外来時に
必ず歩行の様子を観察し、
変化がないか確認しています。
「先月より、歩幅が少し広くなりましたね」
こうした声かけが、
鈴木さんの継続意欲を高めています。
生活環境の見直しも重要
運動だけでなく、
生活環境の見直しも
転倒予防には重要です。
山田さんは、 鈴木さんの自宅環境をヒアリング。
「お家の中で、つまずきやすい場所を教えてください」
転倒の多くは、 実は自宅で起きています。
よくある転倒の原因
- 敷居や段差、電気コードや新聞
- 滑りやすい床やマット
- 暗い照明
山田さんは、 具体的なアドバイスをしました。
「電気コードは壁に沿わせて、 床を横切らないようにしましょう。
夜中にトイレに行く時のために、 足元灯をつけるのもいいですね」
また、靴選びについても 助言しました。
「室内でも、かかとのある履物が安全です」
こうした細かいアドバイスが、
実際の転倒予防につながります。
運動を続けるための工夫
3ヶ月後。
鈴木さんは、毎日の運動を
習慣化していました。
「朝のニュースを見ながら、 椅子スクワットをするのが日課になりました」
運動を継続できた背景には、
いくつかの工夫がありました。
生活の中に組み込む。
「朝のニュース」という既存の習慣に
紐づけることで、忘れずに実施できます。
記録をつける
カレンダーにシールを貼るだけでも、
達成感が得られ、継続意欲が高まります。
定期的な評価
外来時に「片足立ちが何秒できるか」を測定。
変化を実感できるようにしました。
家族の協力も不可欠です。
一緒に住む娘さんにも声かけを依頼し、
サポート体制を整えました。
山田さんは、
鈴木さんの変化を
実感していました。
「歩き方が、以前より安定してきました。
本人も『階段が楽になった』と話してくれています」
小さな変化の積み重ねが、
大きな成果につながります。
転倒してしまった後の対応
どんなに注意していても、
転倒はあり得ます。
その時の対応も、
医療スタッフとして
知っておくべきことです。
山田さんが担当する別の患者さん、
田中さん(仮名・80歳男性)は、自宅で転倒。
幸い大きなケガはありませんでした。
しかし、転倒後に
「また転ぶかもしれない」恐怖から、
活動量が大幅に減ってしまったのです。
「転倒後症候群」と呼ばれる状態です。
転倒への恐怖から活動を控える。
その結果、筋力やバランス能力が低下。
そして、実際に転倒リスクが高まる。
この悪循環を断ち切ることが重要です。
山田さんと田口さんは、
田中さんに丁寧に説明しました。
「転倒が怖いのは当然です。
でも、だからこそ、安全に身体を動かすことが大切です」
転倒直後は、安全性を重視したプログラムから始めます。
椅子に座った状態での運動。
手すりや壁を使った運動。
理学療法士による直接指導など。
徐々に、自信を取り戻していく
段階的なアプローチが必要です。
予防は治療に勝る
転倒は、高齢者にとって
重大な健康問題です。
骨折で寝たきりになるリスクもあります。
しかし、適切な運動により、
そのリスクを減らせる可能性があります。
「転倒してから対応ではなく、
転倒する前に予防する。
これが最も重要です」
薬による治療も大切ですが、
運動による予防も同じくらい重要です。
いや、場合によっては、
予防の方が効果的かもしれません。
医療スタッフとして、 患者さんの
歩き方や体力の変化に早く気づく。
その上で、適切な運動を提案する。
そして、多職種で連携しながら、
継続的にサポートしていく。
結果的に、高齢患者さんの安全な
日常生活を守ることにつながります。
まとめ
高齢患者の転倒予防において、
運動は非常に重要な役割を果たします。
筋力やバランス能力の維持・向上により、
転倒リスクを減らせる可能性があります。
医療スタッフとして、
患者さんの小さな変化に気づくこと。
多職種で連携し、
それぞれの専門性を活かした
アプローチを提供すること。
そして、生活環境の見直しも含めた
包括的なサポートを行うこと。
転倒予防は、
患者さんの人生の質を守る、
重要な取り組みです。
一人でも多くの高齢者が、
安心して日常生活を送れるように。
医療スタッフの日々の声かけと支援が、
その実現につながっていくのです。