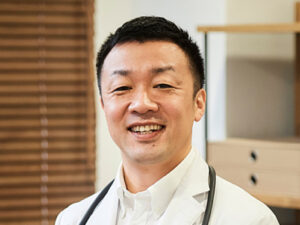「3ヶ月続けば成功」
トレーナーの世界では、 よくこんな言葉が聞かれます。
しかし現実には、多くのクライアントが その3ヶ月を待たずに離脱してしまいます。
なぜ人は運動を続けられないのか。
そして、トレーナーとして どうすれば継続をサポートできるのか。
今日は行動変容の科学から、 クライアント指導のヒントを探っていきます。
行動変容の5段階を理解する
パーソナルトレーナーの高橋さん(仮名)は、 ある悩みを抱えていました。
健康診断で数値が悪化し、 医師から運動を勧められて来た中村さん(仮名・52歳男性)。
初回のカウンセリングでは意欲的だったのに、 2ヶ月目から予約のキャンセルが増え始めたのです。
「最初はあんなにやる気があったのに、 何がいけなかったんだろう」
高橋さんは、行動変容理論について 改めて学び直すことにしました。
行動変容には5つの段階があると 考えられています。
無関心期・前熟考期:まだ行動を変える気がない段階。
関心期・熟考期:6ヶ月以内に行動を変えようと考えている段階。
準備期:1ヶ月以内に行動を変えようとしている段階。
実行期:行動を変えて6ヶ月未満の段階。
維持期:行動の変化が6ヶ月以上続いている段階。
中村さんは準備期から実行期に入っていました。
しかし、実行期は『最も挫折しやすい時期』でもあります。
初期の高いモチベーションが徐々に低下し、 日常の忙しさに飲み込まれていく。
多くのクライアントが経験する 典型的なパターンでした。
継続率を高めるプログラム設計
高橋さんは、 中村さんとの面談を設定しました。
「実は最近、仕事が忙しくて…。 トレーニングの日も疲れていて、つい休んでしまうんです」
中村さんの言葉から、 問題の本質が見えてきました。
週2回60分のトレーニングは、 中村さんの生活リズムに合っていなかったのです。
「それなら、プログラムを見直しましょう。 週1回でもいいんです。その代わり、自宅でできる 10分のエクササイズを毎日の習慣にしませんか?」
高橋さんは、 プログラムを大きく変更しました。
ジムでのトレーニングは週1回30分に短縮。
内容も、自宅エクササイズの効果を高めるための 補強的な位置づけに変えたのです。
継続率を高めるプログラム設計には、 いくつかのポイントがあります。
現実的な頻度と時間
クライアントの生活スタイルに合わせた、 無理のない設定が重要です。
段階的な負荷設定
最初から高い強度を求めず、 徐々にステップアップしていく設計です。
成果の可視化
体重や体脂肪率だけでなく、できなかった動作ができるようになる、 日常生活が楽になるなど、多様な成果を示します。
柔軟な調整
体調や生活の変化に応じて、 プログラムを柔軟に変更できる余地を残します。
モチベーション維持のコミュニケーション
プログラム変更から1ヶ月後。
中村さんは週1回のトレーニングを継続し、 自宅エクササイズも習慣化しつつありました。
「10分なら続けられます。 朝の習慣にしたら、意外と気持ちいいんですよ」
この変化の背景には、高橋さんの コミュニケーション戦略がありました。
毎週のセッション後、 高橋さんは必ず次週の目標を確認します。
ただし、それは「週5回やりましょう」といった 押し付けではありません。
「今週は何回できそうですか?」と クライアント自身に決めてもらうのです。
自己決定。
自分で決めた目標は、 他人から与えられた目標よりも達成しやすいのです。
小さな成功の承認
「1回でもできた」を「たった1回」ではなく、 「1回もできた」と捉え直す声かけをします。
失敗への寛容さ
できなかった日があっても責めず、 「次はどうしましょうか」と前を向く会話をします。
また、高橋さんはLINEでの 簡単なフォローも始めました。
「今日の10分エクササイズ、どうでしたか?」
たった一言のメッセージですが、 これがクライアントにとっては大きな支えになります。
トレーナーが気にかけてくれている、 見守ってくれている。
その実感が、 継続への力になるのです。
医療連携による長期的なサポート
中村さんのケースで、 もう一つ重要だったのが医療連携でした。
高橋さんは、中村さんの了承を得て、 かかりつけ医と情報を共有していました。
3ヶ月後の健康診断で、 中村さんの血糖値は改善傾向を示しました。
「先生から『運動の効果が出ている』と 言われたんです。それを聞いたら、もっと頑張ろうって 思えました」
医師からの評価は、 クライアントにとって大きなモチベーションになります。
トレーナーが一人で頑張るのではなく、 医療機関と連携することで、クライアントを多角的にサポートできるのです。
医療連携のメリットは、 他にもあります。
安全性の担保
持病のあるクライアントに対して、 医師の指示のもとで安全に運動指導ができます。
専門的なアドバイス
薬の影響や病態について、 医療スタッフから適切な情報を得られます。
モチベーション向上
医療データの改善が、 目に見える成果として実感できます。
信頼性の向上
医療機関との連携は、 トレーナーとしての信頼性を高めます。
秋こそ習慣づくりのチャンス
10月は、 運動習慣を作るのに最適な季節です。
暑さも落ち着き、 身体を動かしやすくなります。
「夏は暑くて外を歩けなかった」という クライアントも、この時期なら屋外でのウォーキングを 取り入れやすくなります。
トレーナーの佐々木さん(仮名)は、 秋の特性を活かしたプログラムを提案しています。
ジム内でのトレーニングに加えて、 近隣の公園でのウォーキング指導を組み込んだのです。
「景色が変わると気分転換にもなりますし、 何より楽しいんです」
クライアントの山本さん(仮名・45歳女性)は、 そう話します。
秋の心地よい気候は、 運動への心理的ハードルを下げてくれます。
また、年末に向けて 「今年中に何か変わりたい」という気持ちが高まる時期でもあります。
この時期の入会者は継続率が高いというデータもあります。
トレーナーとしての成長
高橋さんは今、 新しいクライアントの初回カウンセリングを行っています。
以前なら、すぐにトレーニングプログラムの 説明を始めていました。
しかし今は違います。
- 「どんな生活リズムですか?」
- 「これまでの運動経験は?」
- 「何が続かない原因だったと思いますか?」
一つひとつ丁寧に聞き取り、 その人に合ったプランを一緒に考えます。
行動変容理論を学び、 実践を重ねたことで、高橋さんのクライアント継続率は 大きく向上しました。
トレーナーの価値は、 ハードなトレーニングを課すことではありません。
クライアント一人ひとりの人生に寄り添い、 無理なく続けられる習慣づくりをサポートすること。
それこそが、 真のプロフェッショナルではないでしょうか。
まとめ
運動習慣の定着支援は、 科学的な理論に基づいたアプローチが有効です。
行動変容の5段階を理解し、
- クライアントの現在地を把握する。
- 現実的で柔軟なプログラムを設計し、 自己決定を促すコミュニケーションを心がける。
- そして、医療機関との連携によって、 より専門的で安全なサポートを提供する。
秋の心地よい季節を活かして、 クライアントの人生を変える習慣づくりを サポートしていきませんか。